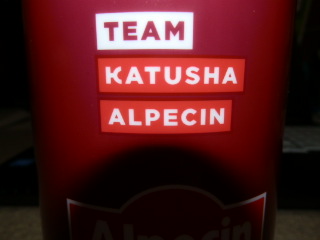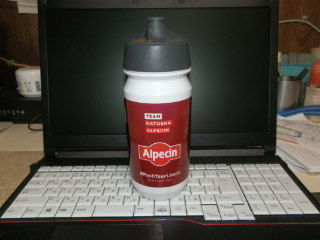□画像が登録されている場合、画像クリックすると拡大表示されます。
□投稿や削除をするときは、画面左上の「管理」をクリックし、パスワードを登録して編集画面に遷移してください。
1画面で5文書登録できます。1文書に画像を3枚登録できます。
痛風のため自宅隠遁中のおしぐれさん、ひまつぶしに中学生相手の「教養教師」をしております。
偉いでしょう、匿名・無報酬・手弁当です。
なお貼付のURLは YAHOO! JAPAN 知恵袋 の一部です。
URL は削除しました。 8/26
いやー みなさん。
お元気でしたかな?
昨日 おしぐれさん ページを確認したら、なんと4人もの訪問者があったでねえがや。
ちゅーこどは、おらの痛風さ心配さーしてくれでおるおひとがちびっとはおったど、それも4人もなや。
そーゆーこんでねーだかや。
でぇーりゃー ありがしたなやなぁー。
んで、くだんの痛風だがなや。
これが はぁ〜 だ、なんともなや はぁ〜なんだぁー。
一向になや 腫れが引かねーんだなや。
歩くと 痛てぇーんだ。
はぁ〜 だがや。
足の写真さ載せる手はあんだけっとがよ。
前回の写真はなや、あんまし評判さ えぐながった。
あ〜んな写真は二度見たくない。
目が腐る。
ちゅー意見も多いでなし、今回はクスリ箱の写真で勘弁してやっかと。
いやー みなさん ひさしぶりです。
おしぐれさんは痛風になりました。70歳代での痛風発症は珍しいのだそうです。
大抵は50歳台で経験するものだそうで、今ごろになって「イテイテ」言っておるのは「お若い証拠ですなぁ あはあは」
大やぶクンが嬉しそうに笑う。
まあ笑うのは構わん、感性豊かな人間の証しじゃけんのう。ティラノサウルスは笑わん。
しかし! いかにも嬉しそうに笑うのは、分別あるべき老医家Drとしては如何なものであろう。
やっぱり同級生のDrの診療所はパスするべきであった。スーパーでプリン体の少ない豆腐とトマトとセロリ、焼酎用炭酸レモン水を買った帰り道に大やぶ診療所の門柱を蹴飛ばしてやった、「イテイテ イテーッ! ばかやろーっ」
右足で蹴っても左まで響くのだわね。
打てば響くって ・・ ばかやろーっ!
計画進行中であった「琵琶イチ(琵琶湖一周路完全走破)ウィズ コルナ号」は頓挫である。とんだことだ。
<画像説明>
意表を突いた新手法。
いきなりの最終段写真ページのご案内でございます。
最終段となれば 「Endキー」 をポチッとですが、ちょっと待ってください。
本編の場合 Endキー で送ると本当に本稿1セット目の最終ページまで一気に飛んで行ってしまいます。
そこには本編タイトルである 自転車大喜利 とは縁もゆかりもない航空機の写真があります。
乗り物違いなだけで縁がない訳ではないとこじつければそうですが、
それはおしぐれさんの気が迷っていた頃の、あの混迷混沌超接待の時代の 「ひこうき雲」 のおハナシでございます。
乗り物というか乗せられモノにはすぐに乗るのでございますよ、あのひとは。
あれは天性の節操のなさとでも申しましょうかねえ、拙僧の貧法では節制の操舵などトンと効きませんのですじゃ。
まあそれでもそこそこに名作の誉れもちらほらにございましたでや、そやからずーっと前のほうのページに確かに残っておるのでございます。
迷い封じのためにかけられた削除禁止の呪いが今も解けないのですなあ。
じゃっけん、それはそれ これはこれ。
これこそのこの本編は、それこそ気合いの草稿でございます。
けっして気の迷いなどではありもはん。
これらそれらがそこに混在しておりますのは、単に脆弱なる本システムのせいでございまして誠に恐れ入ります。
任意の位置に写真画像を自由に置けない現状のシステムはぜんぜん今風でございませんよねえ。
(じゃけんが あのね、 シスを作ったのはあの団塊屋のNさんなんでごぜーます。恐れおおくて文句なんか言えませんでしょーや。 ねえ)
なのでマウスのローラーで静かにそろそろと、数ページ分をめくって写真の処まで移動してくださりませ。
1枚目 : TEAME KATUSHA ALPECIN のロゴです。
なに? それ! のお方が多いことでございましょうね。
お手数でございますが ”チーム カチューシャ アルペシン” で検索を先にお願いできますでしょうか。
さすればワタクシの稚拙な説明でハナシをややこしくしてしまう愚を避けられましょうほどに。
2枚目、3枚目 : UCI登録チーム、 カチューシャ の公式チームボトル A面とB面です。
どちらが表か裏かとか そーゆー断定的なことはワタクシの立場上申せないのでございますが、
3枚目がスポンサー企業 アルペシンさま の社名を印刷したサイドですからコチラがA面になりますね。 絶対ね。
さあさあ よいこのみなさん、さっさと1ページ目に戻ってね。
始まるよ。
第一部 スイス アルペシン
今年も自転車ライダーには大汗の季節が巡ってまいりました。
UVカットの長袖アンダー着用であっても厳しき太陽光は残量乏しくなった爺さんライダーの体力を容赦なく消耗させます。
この時期のアウトドアアスリートにとって水の補給は とりわけ 重要なことになりますね。
「とりわけ」とは昔のサムライ用語では「生死を分ける」という意味でした。
はい、宮本武蔵の時代のことです。
昨今の とりわけ は皿鉢料理の仲居さん用語になってしまった。
断腸の思ひでございます。
おしぐれさんはウォーターボトルを夏用デザインに更新しました。
勘のよい読者さまでございます。
お察しの通り今回のおしぐれさんはウォーターボトルのおハナシです。
海外商品のコマーシャルが印刷されたプラスチック水筒1個でですよ、大胆にもAmazonに対抗した商品レビューをですよ、それも何ページもにわたって書こうというのです。
これはもうナニか特別な狙いのモノと期待しますよね。
なんたって とりわけ ですものねえ。
元商社OBさまはもとより元お役所系だったりの読者さまは「ナニやらキケンな利権の香ほり」に小鼻をひくひくさせます。
「いやーっ ご同輩、長年の習性は忘れておらんとですなあー。 はっはっはー」
それなら書くほうのワタクシだって大変に書きやすくってよーがすよ。
ペテン師だったころは最初のとっかかりに一番腐心したものでございますからねえ。
でもね、ところがね、じつはタダのコマーシャルボトルなんです。
ペテン話だなんて滅相もない、もう何年も前に足を洗いました。
タダというのは先着順の並んだ端から無料で貰えるというタダの意味とほぼ同じです。
どーしても書かねばならぬというほどの悲壮なおハナシではありませんのです。
そのような書き物はおおよそが駄作なのでありましょう、ありましょうがときに意外にふと、なんだかへんに面白いものがあったりする場合がどーかするとありませんか?
それが とりわけて これだなどと、そーんな大それたことを申すつもりはございません。
けっしてございませんのですが、そこはソレ、元ペテン師のサガなんでございましょうなあ。
見た通ーりのことを そのまま 皆さまにお伝えしよーと、はい そのよーにしておるだけなんでございますよー。
本欄お読みの多くの方々はさほどにお急ぎのこととて無いのでございましょう?
なれば他のことは明日以降に移行して、ぜひとも全編通しで読んでみてくださいましな。
それは根気が弱ってトイレの近くなった皆様方には超難儀でありましょう。
ですがこう申し上げておるのは友情のあかしとしてきっと許されると思うからなのであります。
最近は「泣き落としの手」も使います。
ええ 恥だなんて思いませんとも、これは戦略です。
「下を向くなあーっ ボトルを取って水を飲めーっ!」
ブーイングに耐えてボールをホールドする。
ホイッスルが鳴るまで無為なパス回しに徹する。
「談合は汚いことか、唾棄すべきことか、
ばかやろーっ! そんなことは現役のときに結論済みじゃないか」
それこそがワールドカップ FIFA ロシア での現実なんです。勝ってこそカッコいいんです。
「最終結果を見てから評価しやがれ。 オレがジャパンの西田だーっ。
オメらーっ! 文句あっかーっ」
みなさま一読後にはきっと、ここ数年で一番の爽やかで幸せな気持ちになれ ・・ なれ ・・ (もしも)なれなかったなら、それはあなた様の感受性シナプス根の退化が原因かも知れない。
団塊屋さんで良いサプリメントを紹介してもらいましょう。
サプリが効いてシナプスがしっかり強固に繋がって、幸せそうなあなた様の横顔を想像するだけで筆者無上の幸せでございます。
はい 手数料のさらに5パーセント配分で情報提供者のワタクシも幸せになれます。
あらあら まだ始まっておらんかったのですねえ。
はやく本文を始めましょう。
冒頭でみな様に検索のお手間をお掛けいたしましたのが問題のボトルです。
ロシア文字 ”K” は現在暫定世界王者、チーム カチューシャ アルペシン のエンブレムです。
(暫定王者という言い方について。
シーズンの初頭に1度でもシリーズ戦で勝ったことがあれば当分のあいだ暫定王者を名乗る権利が得られます。
スポンサー様に大手を振って報告に行けます。
行けばご祝儀が期待できます。
登録選手全員分プラス監督の分。
ルーフにスペアホイールを積んだメカニックカー、スーパースバルWRCワゴンを軽々と操って選手の後を全速で追う元F1ドライバーの分とシマノから来た日本人メカニックの分。
さらに揺れる移動バス内のチッチンで必死に選手の高カロリー補給食を作り続ける栄養士の分。
合計額は数億スイスフランに及ぶでありましょう。
(えっ! ご祝儀はユーロでないの? という経済通の読者さまに。
あとで申し上げるつもりだったのですがスポンサー様のお国の通貨はスイスフランなのです。
EUに加盟していないからなのですが、自転車レースの通行についてはユーロのEU諸国と同じ考え方です。何の問題もありません)
ちなみに移動バスの運転手はチーム監督本人です。
はい、EU圏外の生まれですが人件費の節減になればと何でもやります。
バスの天井モニターで先頭集団のレース状況を見ながら無線コムで選手に指示を送ります。
はい、ヘッドセット使用ですから道交法違反とはならないと言い張るのです。
おまけにフランス語は話せないうえに営業バス免許なんか持っていません。
でも大丈夫なんです、自転車大好きのEU諸国ではUCIのステッカーを貼ったキッチンバスをタダの大型保冷車として取り扱ってくれます。
それが欧州の文化です。
すばらしい自転車文化ですが、シーズン末期になっても1勝のままの ”元暫定王者” ですと、カッコ悪いばかりか来期の契約が微妙になります。
この時期の監督は青くなったり赤くなったり心労で髪の毛が真っ白になったりと、まるでフランダースの三色旗のようです)
アルプス越えの自転車ライダーは喉が渇きます。
1時間に1リットルもの水を飲むのは決して糖尿のせいではありません。
水冷エンジンの心臓が水を欲するのです。
ツールに使われる水ボトルは写真に見るとおり丁寧ながっしりとした作りになっています。
繰り返される標高差のアップダウンで密閉容器が受ける重力差は累積されると何トンにも相当します。
作りが悪いとモレるんです。
開放容器は大丈夫なんです、密閉容器ほどモレるんです。
月の陰をクイックに回ってアーク地表に接近したUFOのドアが突然開いてしまって乗員のUF人が落っこちてしまったりするのも重力のイタズラなんですねえ。
だったらフタなし開放型でいいんじゃないの?
ダメなんです、登坂の坂は傾斜しているから坂なんです。
フタ無しコップに入れた水は、坂では ”こぼれるの法則” なんです。
ですから標高差と急降坂からの急減速時に発生する首のもげそうな重力に耐えうるがっしりとした超密閉ボトルが求められるのです。
それだけではありませんぞ。
「オラほの選手はなや、命がけで国境のアルプス坂を越えで来たんだ。
命がけだぞ、わがってっかぁーっ。
なんだとぉーっ!
たかが自転車でえらそうに言うなってが、オメーっ このやろーっ!
おしぐれさん 止めねでくれ。
オラはあのヤロさ殴る。
選手はなや、なんぼ苦しい坂でもなや、ケツを上げでギッギどペダルを踏んで来たんだ。
見でみれ、サドルに地中海の砂が積もってっぺ。
海のゾーンを過ぎてからは一度も座らず漕いで来た証拠だ。
山にかかってなや、薄い空気で息が苦しぐってもなあ、選手は故郷オセチア村の酸素を溶け込ませた水さ飲んで耐えるんだ。
自転車にはな、水しかねーんだ。
酸素ビンなんか積まねーぞ、重たくなっちまうからなあー。
オセチアの水さえあれば耐えられるんだ。
あにっ! 空のボトルを沿道に捨てるのは行儀が悪いってが。
勘弁してけろ。
ドーピング検査に回されないよう遠くさ捨てるんだ。
ん、 冗談だよう。
オメ、 一瞬引いたっぺ。
選手はなあ、バイクを軽くしたいからタマシイ以外はなんだって捨てる。
なに、タマシイか?
そりゃー重たいぞ、12グラム もあるのは知ってっぺやー。
んだば 酸素はどーすっかつーとな。
たまに巡ってくる下りで思いっきり速度を上げでよ、 口をいっぱいに開げで空気さ倍吸うだ。三倍吸ったってええどーっ。
いわゆるターボアスピレーション効果っちゅーワゲだあ あっはっはー。
ドーピング規定には抵触しておらんどーっ、文句あっかあーっ。
オラはなや しがねーただの水ボトルだけんど オラほの選手だちのこどが大好きだあ。
だがらよ、ヤロらの水冷エンジンはオラがキッと守ってみせるだし。
スポンサーの旦那さん よーぐ見でおってくらっしょー。
季節はずれの雪で真っ白になったマドン峠さ一番に越えでよ、
真っ黄色のミモザ咲くパリの街にむがって真一文字に降りで来るんだ。
まるでエッフェル塔に突き刺さるように下って来る真っ赤なルシアン色のバイクを見でくらっしょー。
白 黄 赤 はよ、おらほチーム監督の生国 ロシア領 北オセチア共和国 の国旗だあ。
ナニ! 知らない?
ばかやろーっ! 新大関 栃ノ心剛志 の母国として有名な、あのジョージアの隣国だっぺよー。 文句あっかーっ。
見えだらよ 選手の股ぐらのとこさに突っ込んであるボトルのマークさよーぐ見でくらっさい。
そっちでねーし ロシア文字の K でねぐ、Alpecin のほうさ見ろしーっ。
それがよ、一番先にパリの街さに帰っで来るんだ。
スポンサーの旦那、見でやってくんない。
もうじきよ、あんたの会社のマークが一番先にナポレオン凱旋門さくぐるんだあー。 ご祝儀はずめえーっ!」
ボトル大将の男気が聞こえてくるような、水ボトルにはそーゆー気合が込められています。
おしぐれさんは股下のボトルホルダーにこの男前ボトルを納めただけで脚力と心肺力がそれぞれ5%アップしたような、超プラセボ効果を感じておるのでございます。
夏用とはキャップの飲み口にツイストねじり式の開閉機能があって、エナジージェルなど粘性の飲み物でも片手でしっかり補給できるグッドデザインなのです。
そのうえ飲み口は一般的な硬質プラ製でなくやや硬めの軟質ラバーなんですわ。
このやや硬めさが絶妙なんですねえ。
みんなお口が憶えている。
懐かしいピジョンほ乳瓶の乳輪ツイスト乳首みたいだから、選手はソレを口に含むたびマドン峠の麓にある古刹教会の菩薩さまであるマリアローザさまのご加護をひしひしと感じるのです。
でもこーゆー高機能かつモチベ高揚ツイスト乳輪機能の付いたキャップを装備したボトルは、相応にお高いからアマチュアは購入を逡巡します。
自費ではなかなか手が出ないのが実情なんです。
その点プロツアーの契約選手たちは飲み切ったボトルを沿道にポイと投げ捨てます。
ポイするときの格好の冷徹さがまあカッコよいこと。
おしぐれさんも一度はやってみたいと思いますが諸般の事情で出来ません。
これからもないでしょう。
プロは少しでも自転車を軽くし、さらに空気抵抗も低減させて速く走りたいと考えます。
次のサービスポイントでよく冷えた新しいボトルを貰えると分かっているから捨てられます。
スポンサーからの支援が豊潤な有力チームはボトルにドリンクがまだ十分残っていたって捨てられます。
マリア様の乳首を捨ててもよいものなのか、などど軟弱な迷いはありません。
男には、勝つためには捨てねばならないものがいくつかあります。
そのなかで一番捨てやすいものは何か? 義理か 名誉か 意地か 女か?
そんなこと考えているヒマはありません。
それほど軽さはイノチです。
迷わずポイします。
それを見たおしぐれさん、熊の毛皮の尻皮を着けて斜面の枯れ葉を滑り降り、水の走る峡谷のふちを懸命に走ってボトル型をしたマリア様を拾い、胸に抱いて峡谷を渡り、冷たい谷川の水で洗って持ちかえる。
そしてありがたく懐かしく大事に使わせていただくほうのひとですから更新はたまにです。
憎らしいことに人気のプロはそーゆー拾うひとを意識して、不滅インキのマジックペンでサインなんかしているのです。
そして深い谷底めがけてポーンと投げるのです。
バカヤローッ !
今回は有償で買いました。 横流し品が密林王で〇〇〇円でした。
那須の谷川沿いにはまだ母子熊がいるし、これからはマムシが出るのです。 拾いには行けません。
余談ですが今春、雪が全部消えて水かさの落ち着いた那須山麓の川筋でなんと、本邦ではすでに絶滅したとされる ニホンカワウソ が相次いで目撃されたとの情報がありました。
「ロマンですねー。 静かに探してみたいですねー」
という那須町副町長と産業振興係長の嬉々とした談話つきで地元紙下野新聞に報じられて以来、那須余笹川周辺の週末はにわか探検家でたいへんな賑わいです。
無料駐車場には地元アウトドアショップの探検グッズ販売車のほかに、焼きトウキビ・焼きそば・いか焼きと焼き物系の屋台が並んでいます。
これから気温が上がれば当然かき氷屋も出ますね。
那須高原牛乳のソフトクリーム屋が出店していないのは賢明だと思います、どーせ一過性のモノですからねえ。
誰が流した偽報なのかは安易に想像がつきますが、偽報だと言ったらこの界隈の道は走れなくなりますから黙っています。
ここは那須町の地域密着チーム・那須ブラーゼンのテリトリーなのです。
役場の委託広報カーがルーフにスペアタイヤを積んでパトロールしています。
宇都宮ブリッツェンのジャージは町の境界で脱いで走るかUターンするしかありません。
沈黙は金でございます。
探検隊のみなさん、熊とマムシと広報カーには気をつけてくださいよ。
それと、もしもロシア文字で K のロゴ入り500ccくらいの樹脂ボトルを見つけた際は迷わず団塊屋に連絡してください。
薄謝と共に喜んで引き取らせていただきます。
そもそもこーゆーPRボトルは、本来は無償でイベント会場のファンに配られるものなのです。
でもUCI上位チームのモノはプレミアムがつくのでそこに利権を見い出す輩が必ずいるんですねえ。
今回の無料分も日本で一手に引き受けたある海洋団体の会長さんが、アベさんのお友達なのをいいことにアマゾンを介して高値で売ろうと画策。
おーっと口は禍のもと。
しゃべり過ぎは老練なはずの財務大臣だって身を危うくいたしております。
沈黙は金ですなあ。
で、カチューシャです。
このチームはロシア初のロシア発自転車ロードチームです。
選手は室内スプリントレースの元RUS五輪代表など剛脚者ぞろい、ツール ド フランスなど最高位イベントにも出場権のあるUCI規格のAクラスチームです。
ですがプロとなればロシアチームといえども自転車ロードレース界は西側資本主義のルール適用です。
ですからそれに習って企業スポンサーを求めることになります。
テニスのマリア・シャラポア選手がアメリカに渡ったのと同じ理由ですね。
さてスポンサーになろうという西側有力企業ですが、日本のチーム ニッポ(日本舗道)ならなってもよいがロシアのチームでは米のトランプさんがなあ。
と躊躇します。
そりゃーそうです。 金喰い虫の自転車UCIチームをスポンサードするということは、
北海道でトウキビ型の宇宙ロケット産業を支援するというホリエモン的無欲のボランテ精神と覚悟と資金力が必要です。
そこでスイスのアルペシン社です。
かの国は東西問題にはかねてよりニュートラルなお国がら、育毛シャンプー で世界トップシェアのあの有名なアルペシン社が手を挙げたのです。
なぜなら、提供先が カチューシャ だからです。
これ、ものすごい国際的シャレでないですか。
座布団5枚級です。
さらに申しあげるなら。
先にチーム監督の髪の毛がツール成績の不振による心労で真っ白になったと書いています、このあたりですでに育毛シャンプー アルペシン社への布石を打っている。 さすがですねえ。
カチューシャはロシア女性の名前に多い 「エカテリーナ」 の略称・愛称ですが、なぜか日本では女性の髪飾り・髪留めのことですよね。
AKB48がそう決める30年も前に当時の青島幸男東京都知事が命名したのです。
天才バカボンのママもたまにカチューシャご着用で登場していましたから赤塚不二男氏も公認しておったことは間違いない。
なぜ命名権者を青島氏説で定着したかというと、許認可権限に大きなチカラを示した氏の実績を重んじてのことかと思います。今となっては深く追求するほどのことではないでしょう。
野坂昭如氏でもよかったと思いますし大橋巨泉氏が原作だとする説もあるようです。
みなさん秘かにハゲを心配なさっていたのですねえ。
アルペシン社が極東の国のそれらの動きを知ってか知らずかは知らないのですが、知らないでは洒落になりませんからスイスイと知っていたに違いない。 スイスですから。
というワケで洒落の集大成であるチーム カチューシャ アルペシン のボトルを手に入れたおしぐれさん、
気つけにレッドブルを添加したポカリスエットを満杯に入れて今日も炎天の渡良瀬ロードを走っています。
第二部 下野国 渡良瀬野
渡良瀬川の源流部である日光足尾山地は、明治の国策であった古河鉱山の粗銅精錬高炉から絶え間なく排出された亜硫酸ガスに晒されて草木は死に絶えました。 動物も去りました。
その中には超レアな動物、もしかしたら霊長類かも知れないヒマラヤ系 イエティ も含まれていたといいますから大そうな損失です。
足尾山地は今もハゲ山の峡谷なのですが、80km下流の渡良瀬ラムサール湿地まで下れば真っ平らで真緑の草原の中に自転車ロードが延々と続く風景に変わります。
山を見てからここに来るとなんだかホッとします。
ホッとしたばかりで恐縮ですがこの真っ平らの草原、じつは越後・會津との分水嶺である日光足尾山地に降った雨が草の根の土留めを失って丸腰となった山肌を容赦なく削り取って沢々を埋め、さらに渡良瀬川を流れ下って来て堆積したあの毒土の上に成り立っているのです。
ええ 忌まわしき鉱毒を土砂ごと封じ込めて出来た大湿原の中で、たまたま毒気の薄かったごく一部の部分が乾いて出現した草原なのです。
なんという皮肉なのでしょう。
古河鉱業所の高炉下を流れ下って来た水は栃木・茨城県境の渡良瀬遊水地まで来てピタリとその流れを止めました。
キッと まなじり を据えたその先に、茨城県古河市の高層ビル群が見えます。
どーしますこれ。
若い頃のおしぐれさんならひと暴れしてしまいますよねえ。
「父祖の仇 憎っくき古河め、我らはついに追い詰めたり。
おのおのがた よっく聞け。
我らがうぶすなの地、渡良瀬 谷中村廃村の恨みを晴らすは今ぞ。
遠慮はいらぬ、封じてきた大太刀の緒を放て。
覚悟はよいな、いざ 参る!」
大義名分に不足はありますまい。
栃木と茨城の仲がいまひとつなのは北関東経済圏の軋轢バナシのハナシではないのです。
野州下野(後の栃木)に綿々と受け継がれる明治最後のサムライ、田中正蔵翁 のDNAなのです。
あれから百年以上が経ちました。
当時鉱毒の半減期は百年といわれたものですが、はたしてどうなんでしょうねえ。
おしぐれさんは幼少期からここで走っていましたから蓄積された総被曝量というものはどーなんでしょうか。
どーなのかは分からないのですが、おしぐれさんはすこぶる元気なのです。
たぶん異星から来た人間だからなのでしょうねえ。
ここには地番がありません。
遊水地と呼ばれるだけです。
昭和の初めころは おばけ沼 と呼ばれていました。
いちど迷い込んだら方向感覚が狂って帰れなくなるからです。
地磁気が変なのかも知れません。マンガン鉄も含んだ大地ですからねえ。
湿原内にあるハート型の谷中湖にはアマゾンから来た半魚人が住んでいて、迷い込んだ茨城の者だけを喰うとのウワサもありました。
ありました と過去形にしているのにはワケがあります。
彼は今でも谷中湖の最深部にアンカー鎖で暫定設置された環境観測塔の喫水鉄骨部に棲んでいます。
水位が変化してもアンカー繋留ですから喫水部は見え隠れなので隠れ家に最適なのです。こんなことは公表できません。
環境計測値は無線で基地局に飛ばされ電源はソーラー発電なので定期メンテ以外に人が近づくことはありません。
メンテの日は前日までに湖畔に作業船が航行する旨の予告看板などが設置されます。
これは漕艇競技やヨットのチーム向けの告知なのですが、当然半魚人もそれを読みます。
バイリンガルの彼は漢字もひらがなも読んで理解できます。
彼は静かに中ノ島のほうに一時疎開し、深く潜水して作業員が去るのを待ちます。
半魚人がひとを喰うことなどはないのです。
彼は顔に似合わずグルメですから、絶対旨そうには思えないケチなうえにチビでデブな茨城の者など食いません。
彼は白身魚をメインにヨシの新芽など水生野草や淡水海苔のようなミネラルグラスを食べます。
湖の魚種は豊富で、鯉フナ鯰のほか漣魚や雷魚やバカ貝や川で獲ったシジミもバリバリ食べて大そう元気です。ときには鴨も捕らえます。
焼き鳥にしたらよいのですが観測塔は火気厳禁ですから生食です。
塩もタレも無しです、なんとワイルドな。
季節で鮎も入湖してきます、たいへん美味しいと言っております。
鮎を追ってカワウ(川鵜)が渡良瀬川上空を飛んで来ますが、谷中湖には着水しません。
半魚人がいることを知っているからです。
カワウの食害から渡良瀬を守っているのは実は半魚人なんですね。
彼の一番の好物は何といっても鯰です。アマゾンでも食べていました。
刺身で食べるときデンキでビリビリしたらワサビいらずなんだそうです。
アマゾン鯰の三相交流と違ってアジアン鯰は単相でやや弱いながらもしっかり発電機能があるんだそうです。
夜間のトイレ照明にこのデンキを使っているとか。
そうそう 冬にはワカサギだって獲れますし大型の白鳥も飛来します。
これは鴨より美味しそうですがロシアから来たと聞けば食べられません。
名前を聞いたらカチューシャだっていうじゃありませんかあー。
食うものに困らないということは良いことです。
人格に乱れが生じませんね。
あとはキレイで優しい女半魚人が来ればねえ・・。
あと百年はここに居たいとも言います。
彼は肺とエラのどちらからでも呼吸でき、冬は凍結寸前まで下がる水温の湖にいて平気に元気です。
鉱毒うんうんはアマゾン生まれの彼には関係ないみたいです。
へその周りのコバルト色の鱗が毒を中和する秘密だとおしぐれさんは睨んでいますが、「1枚欲しい」 とは口にしません。
友だちにそーゆーことは言わないのが渡良瀬の原則です。
じつはヒマラヤ系 イエティ も一時ここに暮らしていました。
ですが夏場の暑さが彼の命を縮めることになりました。
半魚人は今でもそのことを悔やんでいます。
「あのとき彼は足尾から逃れて来た疲れが出て体調を崩していた。
おれがヨシの葉と茎で日除けのヨシズ小屋を編んでやっていれば彼は長生きできたんだがなあ。
ヨシを編む棕櫚縄のシュロを探しに慶良間諸島の棕櫚間島まで行っている間に死んでしまった。
田んぼに転がっている農事用ビニール紐で編んでも良かったんが、あのころのおれは本格ヨシズを作ることにこだわりを持っていた。
益子焼きの濱田庄司に影響されていたから民芸作家として廉価な作品を目指してはいたが、縄くらいは本格シュロ縄を使いたかった。
だから渡良瀬より20年も早くにラムサール登録されていた慶良間諸島のシュロを採りに行っていたんだ。
泳いで行ったから縄を背負って潮流に逆らいながら帰ってくるのに手間取ってなあ、2年もかかってしまった。
イエティのやつ、「赤麻沼(旧おばけ沼の正式名称)産の麻縄でもいいから早くヨシズが欲しい」 とは言えなかったんだなあ。
死期が迫っていると知っていればクマネコお急ぎ便で取り寄せも出来たんだが、すまないことをした」
これらの事実をいまさら公表はできません。
おしぐれさんは最後のひとりとなった 渡良瀬友だち の平穏な暮らしをそっと見守っています。
一方渡良瀬の岡地である草原には簡易ゴルフ場などが出来ていますが民有権は認められておらず国有の扱いです。
ですがもぐりで畑を作っているひとを何人も知っています。
このような場所ですから耕作面積は意外に広い。
北海道富良野のような風景のところさえあるのです。
ところが上流山地に大雨が降って渡良瀬川が増水し、遊水地に洪水吸収の措置発動が命ぜられて数百の水門が一斉に遠隔操作されると富良野畑など30分で水没します。
水流は畑の作物を根から掘り返し何週間も水は引きません。地形も変わってしまいます。
それでもよいかとの了解と暗黙の許諾とが入り混じってとてもグレーかつ大人な地帯です。
よーするに、どちらも相手のすることに指図はしない、文句ははさまん、しかし渡良瀬の治水に関しては唯一の絶対服従ということです。 大人ですねえ。
渡良瀬は東京近郊に大空港を造る構想の候補地を成田と争ったこともあります。
しかし最終段のところで一歩踏み出せないナニかを視察団の先生方は重く感じた。そーゆー日本有数の空白の地域です。
他にあるとすれば下北恐山周辺と鳥取砂丘だけでしょう。
土が流れて岩だらけになってしまった足尾山への植樹は木の苗を運ぶと同時にそのための土も背負って運ばねばなりません。
これが山の緑化が遅々として進まない要因です。
ヘリコプターから種を蒔いたこともありましたが、受け取る大地に土がないのだから発芽しないのです。
足尾の山には猿も熊も猪も鳥の類もいません。
隠れ家となる森がなければ食べる木の実も育たないからです。
おしぐれさんは少年時代にサンショウウオを探して沢を遡ったことがあります。
小型の両生類は沢の苔と腐葉土中に溶け込んだミネラルで生きています。
たまに虫も食べます。沢蜻蛉(サワカゲロウ)の幼虫つまりカワゲラやザザ虫などですね。
大型動物との遭遇リスクがないからマムシ除けの蚊取り線香さえ腰に下げていればナイフなしでも安全な山でした。
蚊取り線香ですか? はい 徳川様の杉並木の杉香料によるフィトンチッドは蛇よけに有効なのです。
そんなこと日光三山の山々では散々に常識だっぺや。
獲ったサンショウウオは東京から来る強精剤ブローカーのおじさんによい値で売れました。
ええ けな気な少年は学費の足しにしたのです。
種類はトウキョウサンショウウオという小型のもので保護種指定以前の昔のハナシです、いっぱい獲れました。
特別天然記念物指定のオオサンショウウオも獲れていれば紅顔の美少年は博士号取得までの学費を稼げたのでしょうに残念です。
渡良瀬ロードの南端は利根川ロードを経て江戸川サイクリングロードの左岸・右岸に接続します。
つまり足尾から東京ディズニーランドまで渡良瀬サイクリングロードは土地土地でロード名称を変えながら一歩も市街地には降りずに繋がって行けるのです。
つまりつまり、イージューライダーの北米横断ルート66みたいなもんですなあ。
まだ通して走ったことないけど・・。
渡良瀬の沿道なら、ここなら心拍にやさしいのです。
心臓には銅も亜鉛もマンガンも必須ミネラルでやんすからねえ。
うっひゃーっ こっちのイヤミな洒落のほうが座布団6枚じゃないの。
どーすんだっぺよ、この出来のよさは・・。
ちなみにですが、亜硫酸ガスによるハゲはいったん罹患したらアルペシンだってスカルプだって薬効は期待できません。
(ちなむな! ってですか。失礼しました)
足尾の山々では細々とした植樹活動がもう100年以上も続いています。
ですがいまだ山肌はハゲ茶色です。
数行前に書いた状況は今も続いているのです。
「どうしたものか植樹の気運がいまひとつ高まらないんです。
有志による植樹も毎年5月のみどりの日だけのバーベキュー付きお遊びイベントだからダメなんです。
国がもっと本腰を入れてかからなければダメなんです。
植樹も植毛も育毛も、毎日本気でお手入れしなければダメなんです。
聞いていますかっ、 総理!」
なんだか国会中継の参議院予算委員会における 森まさこ 議員の鋭い質問口調になってまいりました。
テレビ見ながら書いていてはダメなのですよ。
明治に始まった足尾の粗銅生産と引き換えに起きた日本公害の原点は、日本の世界戦争への準備だったから一日当たりの生産量をあせり過ぎた結果です。
お手入れをせずに一日の自然回復量をはるかに超えるブラックさで髪をかきむしるように無謀操業していたんですねえ。
世界戦はロードチャンピオンシップに任せましょうよ。
そしてヘルメットの内部は昔も今もたいへんな汗の操業です。
次の戦士と交替したら、選手はゴールしたら、ビールの前にお風呂でアルペシンの育毛シャンプーでしょう。
はい しっかりコマーシャルを果たしましたよ。
いやいやー お見事でした。
それにしてもおしぐれさん、ナニよその元気さは?
渡良瀬湿原ではナニけ? マカ草も生育するのけ?
んだば、団塊屋が販売に乗り出すべかねえ。
追伸
宇都宮市からの 「ねんりんピック 2020 県スポンサード登録選手決定通知書」 がまだ郵送されません。
郵便受けに名前が書いてないからでしょうか、それとも市県民税滞納だからでしょうか。
「名人〜ん。 いますかー お邪魔しますよ〜」
「おお これは剣志郎どの、よう参られた。 ささ入られよ、なにもう入ってワシのロッキンチェアーに座っておるってか。
そーか それならそれでもよいがの剣志郎どの、そのへんのものに汚い手で触れてはならんぞ」
「なにそれーっ! ボクはまだなーんにもしていないよ」
「まだ がいかん。 おぬしは目を離すと何でも触って口に入れる」
「赤ん坊みたいに言わないでくださいよー」
「おぬしも知ってのようにワシの工房にはケミカル剤の乾燥を待っているモノがそちこちにある。
養生中の蒸気には弱いが毒性もあるでな、安定乾度になるまでは触れてはならんのじゃ。
こらあーっ! 座ったまま動くでねーっ。 息も止めておけーっ。 まばたきするなあー、ほこりが舞うべえーっ」
「ほこり? ですか」
「うむ 当工房の梁や天井や壁にはな、特殊なほこりダニが代々住み着いておるんじゃ」
「家ダニですか?」
「いや ダニー家田だ」
「へっ? パラキンですか」
「うむ 隣の家田さんちへ食料調達に行った際に誤って花王のダニパラエースを舐めてしまった阿呆ダニが帰って来てからワシの作業台の下で死んだ。
その死骸から発するダニロートとケミカル剤のケミとが接触反応すると酸化触媒作用が起こるんじゃ。
そのとき熱と同時に生成されるのがダニカルパラリン酸なんじゃ」
「なんだす その 無理ごじゃっぺな命名は?」
「うむ 近くにいて接触吸入した者をな、浜名湖うなぎの幼生であるロックンシラスのような半透明人間「ヤマハロックの ダニー東名」に変身させる凶魔の気体じゃ。
無念に死んだ阿呆ダニが人類に一矢報おうとする ”気” じゃとワシは思うておるんじゃよ」
「ぎっひー 出直しますですぅ〜」
「まてっ! 帰るのはかまわんが手土産は置いて行け」
「えーん 手土産ないから帰れません」
「だったら最初から来るな。 他家を訪ねる際の作法というものを知らん男にはまったくもって困ったものじゃ。
それでよく剣士を名乗っておられるのう」
「あっちゃー、作法 でございますかあ〜。
卜伝流 鍋ふた無刀派指南 鹿島 剣志郎。 奥儀皆伝の後の気のゆるみ、慢心にございましたっ。 お恥ずかしゅうござりまするーっ。
かくなる上はここにて腹を切りますゆえ、先生には介錯のお慈悲をいただきとう存知まする」
「ふん おまんなあ、大げさな口上はサムライびいきの世論を味方につけてかかる事態を穏便に乗り切ろうとしておるのであろう。
うつけめが! 介錯が欲しいてか。 なればオートマチック逆転2枚刃電動カッターのスイッチくらいならいくらでも押してやるぞ」
「ひえーっ お見通しの如くでござりまするぅー。 恐れ入りましたぁ〜。
オート動作の逆転2枚刃電動カッターだけはお許しくださりませえ〜。 フランス革命ギロチン台のほうがマシでございますうー」
「ふん、やっぱり出直しレベルじゃのう。
いいか おまん。 いくら狭い作業場とはいえ広さを感じさせる入りかた、アプローチの作法というものがあろう。
来るなりいきなり房主のロッキンチェアでは、まるで四畳半の距離感ではないか」
「あのー 四畳半と申されましたか? 三畳と思うておりました。 そーですか 旧建築基準ザル法の六畳だったんですか? なつかしい団地サイズ規格ですなあ」
「おまんなあ 殴られたくてここに来たの?
せっかくの休日というに、そ〜んなにご家内といっしょに家にいるのはつらいか」
「ひえーっ そーゆーおハナシはお許しくださりませ〜」
「ああ 出来るならワシもしたくはないものじゃ」
「話題を変えましょーよ 名人。
広さを感じるアプローチの距離感って、あるんですか そんなの」
「ああ、遠近法で発声しながら接近するんじゃ。 ♯ ご め − ん く − だ さ り ま っ せ ー ♪ っ てなあ。
ええか。 リズミカルに高らかに、そして清楚に、格調テノールの音域が必要じゃな。 おまん できるか?」
「格調テノール ですか、エタノールを変調した密造酒のことじゃないのね」
「おまんわざとトボケておらんけ?
師匠のワシをおちょくって浮世のウサを晴らそうってか、馬鹿ものの短慮もののうえに小心阿呆なる恐妻家め」
「そこまで言いますか」
「ええが よっく聞けよ。 テノールはのう、グライダーの着地アプローチと ♭ おーんなーし じゃあー ♪」
「パチパチパチ 名人、おみごとですなあ。
んで、遠近のテノールの発声がグライダーの着地とおんなしとは如何なる由縁でございましょう?」
「ああ、この世は音楽じゃ。 そーは思わんか」
「あっひゃー。 音楽ですかあ〜。 これまでのおしぐれさんシリーズにはない衝撃的イントロダクションでございます〜う」
「ああ、ワシな本来はミュージシャンなんじゃ。 こー見えて幼少のみぎりはウィーンの賛美歌隊、長じて清楚でヘビーなロッカーになった」
「ぎょえーっ! 冬の竜飛岬の更衣室ですかあ〜」
「なんじゃ それ?」
「はいーっ 秋の大掃除のあとは誰も来なくなって竜蛇の巣になった海峡パラグライダーマン用ロッカールームですうー」
「ふんっ 無理がありすぎる。 どーゆー落ちを狙ったものか作家の意図がわからんちゃ。
だいたいなあ 竜蛇ってなによ。 タッピーなヘビーロックの枕詞か、馬鹿者め」
「あらー これでは受けないのけ? 今回はレベル高いわねえ」
「ワシがロッカーの素性を隠して生きてきたのはな、こころならずもじゃったが食うための仕事を得る方便じゃったんじゃ。 マリアさまも許してくれた。
じゃがいよいよ引退してグライダーを大空に放ったときからワシは自由なロッケンローラーに戻ろうと決めたんじゃ。
マリアさまも祝福してくれたぞ」
「げっひゃー。 これまでも十分に自由な六軒長屋の浪々人生だったじゃーないですかあ〜。
同じことは自転車を始めたときにも聞いたように思いますぜ、「俺にかまうな 俺はヒッピーライドの旅に出る」ってねえ。
ところでマリアさまって 山下達郎夫人 のことですか?」
「そうか、そんなことを言った時代もあったか。 じゃがな、ヒッピーも山下も 過去のことにはかまわんでくれ。
マリアさまか? ツール ド フランのマドン峠の麓、 ローザ教会のマリア菩薩さまに決まってっぺし、もの知らずの馬鹿たれめー」
「げっぴー 馬鹿出し3度めぇ〜つ。 馬鹿座布団1枚! な〜んちゃって」
「無視して先に進めるべし。
さてとオメさん、ほんとに手ぶらか? よく来れたのう」
「あいかわらずですなあ。 ロッケン名人」
ボクは自転車で来たんだもの手みやげなど持てません」
「うん まあよかろう、オメさんは白いリムジンで送られて来たって手ぶらじゃ。
なんたってオメさんは楽丼カードっちゅう魔法のナニを持っておるでのう、手ぶらで来ても大丈夫」
「なんですかそれ、名人あんたもしかして 腹が減っているの?」
「ああ もう昼どきじゃ。
ワシな、このあいだ表の通りのうなぎ屋の前でな、うなぎ屋主人にバッタリ会ったんじゃ 「最近さっぱりですなあ」 って言うんだよ。
たまには行ってやらんといかん」
「たまにはってあんた、先月ご馳走したじゃないの。 しかも特上をさあ。
それになんですよ、うなぎ屋の前でうなぎ主人に会うのはバッタリじゃないでしょう。
主たる目的を確固に持ってそこへ行ったとするのが当たり前の順当かつ万人がうなづく司法な判断です。
あなたは表通りを白昼ひとりで歩けるよーな真っ当なおひとではない、相当なリスクを承知と覚悟でソコへ行った。 違いますかあ。
あなたはうなぎ屋主人をその八つ目な眼力で無言に脅し、特上うなぎの忖度を得ようとした」
「ずいぶん断定するねえ。 検察は状況だけで予断を持ってはならんぞ」
「いーや 十分なる予断にてキッパリと断定させていただきます。
うなぎ主人の 「最近さっぱり」 の意味はね、お客の入りがさっぱりで売り上げが下がる一方だということです。
名人のことは 「ぜひ来ていただきたい上客さま」 と思っていないことくらいはいくら鈍感なあなたでもさすがに分かった。 なのでその日はすごすごと帰った。
定年後はすっかり落ち目の名人のことを表通り商店街では 「かつての虎の衣を借る収賄魔・わいろマン」 とウワサになっていますからねえ」
「おまん、師匠のワシをずいぶん落としめしてくれるじゃないの。
いいか、グライダーマンに ”落ちる” ”下がる” は禁句じゃ。 株式マンもおなしじゃろ。 以後こころしておけ」
「はいっ がんばります」
「よっし、ところで先月のその節は世話になった。 うな特は美味であったぞ。
ついてはと言ってはなんじゃがな剣志郎どの、ワシな、死ぬまでにいちどは特特上を食してみたいと考えておる。 おぬしとなあ」
「げっ」
「グライダーマンにとって上のさらにそのうえの特上のもっとうえ、特特上は成層圏だ。
風の又八郎も吹かれたことのない高さである。 そこは セントアルバトロス しか昇ったことのない至高の高みであろう。
メニュー名は 地中海風サーマル風のアルバうな特 だ」
「イタリア料理ですか。 うなぎ屋で?」
「うむ、現代は蕎麦屋も寿司屋もグローバルに商売せねばならん」
「地中海風はわかりますが、サーマル風ってなに?」
「バカっ! サーマルふう ではない。 サーマルかぜ じゃ。 翼長3mのアルバ級グライダーを成層圏まで押し上げる上昇気流のことじゃ」
「ほう それはようございましたなあ」
「それだけ?」
「へっ?」
「さあ 行きましょう とか言わないの?」
「悪いところに来ちゃったなあ。 んじゃー こーしましょう。 出前をとるんです、特特うなのつまみ焼きだけをね」
「なんじゃ それ」
「だって先月名人とお店に行ったときはうなぎの焼けるまでお酒を飲むことになりましたわなあ。 うな骨をつまみにして。
うなぎ屋もよーく承知していてうなぎはわざとゆっくり焼く。 その間お酒がどんどん進む。 そのうち、
「やい うなぎ屋、かば焼きはつまみ用に薄味に仕上げろ。 うな骨はあきたからうな皮を焼け」
とか言って結局うな重は食べずに特上うなのつまみ焼きと松たけ肝吸いお椀と会津寒仕込みの特上酒だ。
よーけ飲みましたなあ。 松たけは松茸でねぐ松と竹だったけんどねえ」
「うむ、梅はうなぎと食い合わせが悪いでな松と竹なんじゃよ。 よーく計算されたギャグじゃろう。
おしぐれさんシリーズの作家は只者でないのう」
「無視 無視。
さらに店主はあんたと結託していると見え、うなぎ屋のくせに
「フグ焼きもありまっせ」
なあ〜んてねえ。 商売熱心なことおびただしい。
こーゆーお店にあんたと行ったれば自転車のタイヤを買おうとしていた予算を全部使ってしまうことになる。
よって出前は特特うなのつまみ焼きのみ、酒はこちらの台所の隅にあるやつで済ませます」
「フグ焼きはないの?」
「ボクがコンビニまで走って ”ふくちゃんのフグ焼き風かまぼこ” と ”松たけの香りお吸い物の素” を買ってきます。 お湯沸かしといて」
1時間後。
「おい もう酒がないぞ。 会津寒仕込みはどーした」
「ふぁい ボクがコンビニまで走って買ってきます」
「うむ、”ふくちゃんのカニかま風”も買ってこい。 いや待て 自転車では危ない、コンビニのほうから出前させろ。 ワシはナーコのゴールドカードを持っておる。 残高を使い切ってからしばらく現金チャージをしておらんがポイントの分はきっと残っておるぞ」
「名人〜ん カニかま風でねぐ ”かま風カニ缶” のゴールド焼きでげしょ。 はよ電話して。
なに! NTTの電話は解約した? あんたそれ倹約のつもりでそーしたの?」
「そーやぁ」
「そーですわなあ。 年に1度も使わない固定電話に基本料金払うといのはおかしい。
設置はあるが使わないお客からは基本料金は徴収せず、回線保守料金の年150円だけにすべきだ」
「そーじゃ、そのとーりだ。 じゃけんがこのおしぐれさんシリーズはのう、実在の企業を指してその経営理念をあれこれいうことはしないのが基本コンセプトなんじゃ」
「名人〜ん あんた ええひとやなあ〜」
2時間後。
「まて、それを弄ってはならん。 不意にペラが回って危ない。
コラッ 外してあるバッテリー線を繋ぐんじゃないって言っておろーが。 触るな」
「名人 プロペラは飛行機でしょーよ。 なんでグライダーにペラがあるの? んーなの反則でねーけ。
ボクらのロードバイクに内緒でアシストモーターを付けたよーなものだ」
「うむ たしかに航空法にいう有人グライダー実機にはペラも動力装置もない。 あるのは充電式無線機と翼に繋がったワイヤーを操作するペダルとハンドルだけだ。 エアコン、トイレはもちろんバックミラーさえない。
ところがだ、そこにぶら下げてあるワシのグライダー模型機には小さいながら立派なペラが付いている」
「ふん ふん」
「実機も模型機も航空機じゃからなんといっても空に浮かばにゃハナシにならん。
じゃがグライダーとして国交省と総務省に登録した実機はエンジンにしろ電動にせよ動力装置を持たない。
そーゆー約束で優遇税制が適用されておる。 排ガスの100パーセントゼロエミッションだからだ。
「ほーっ そーゆーものけ」
「そこで上空までの打ち出し装置が必要となる」
「ふん ふん」
「電動ウインチ等で引っ張る ”手綱式” 火薬で打ち揚げる ”カタパルト式” 小型飛行機に曳航されて飛び立ち、十分な上空まで浮いたらワイヤーが外れる ”子捨て式” さらには自らワイヤーを切る ”身投げ式” などがある」
「ほえーっ! グライダーは優雅な飛び姿のわりには空に浮くまでが超スパルタンな乗り物なんですねえ」
「そーや。 じゃが優雅ゆえに荷室などはない。 計算外の重量は負担できないうえ好天の日しか飛べないから災害救助になどは使えない。
ひとさまのお役に立つことはなあ〜んにもないのよ」
「ほえー」
「あれはフライヤーの自己満足だけなのよね。
しかもよ、ひとたび落ちればひとさまに多大な迷惑をかける。 音もなく落ちてくるからオスプレイより始末が悪い」
「なんで国交省は禁止しないの?」
「空へのロマンとしか説明がつかん」
「ひえ〜っ 荒井 ゆーみん の世界ですかー」
「んー?」
「ひこうき雲 ですう〜」
3時間後。
「さて話しを進めるぞ。 模型機のほうじゃが紙ひこーきグライダーの時代はタコ糸で機体と結び、一方の端を持って少年は向かい風の方向に懸命に走る。 そーやって揚げたもんじゃ」
「はいーっ 憶えておりますともー」
「ぐんぐん揚がって行ってタコ糸が少年と一直線の角度になって、ついに白い機体が下を走る少年を追い越したら」
「追い越したら?」
「握ったタコ糸を クンッ と引く」
「クンッ と引くとぉーっ?」
「フックから離れた白い機体はフイーッと」
「フイーッとぉー?」
「白いひこうき雲になる」
「あっひゃーっ ボクは泣きそうですぅ〜」
「お客さんたちぃ〜 ええ話でんなあ〜。 八つ目うなぎの胡麻山椒あえ 焼きまひょか」
「やい うなぎ屋。 ワシらはいつからオメんとこに来ているんだ、ワシの工房で飲んどったはずじゃがなあ。 ここは焼き鳥屋か?」
「へい 焼きうなぎ屋でがす。 オラ家では備長炭でねぐ文明開化以来の伝家の宝炎、明治瓦斯の木炭ガスで焼くんでがす」
「うなぎ屋、その凄い木炭ガスの話しは次回に特集するでよ、すまんが今日はあっちに行っていてくれんかなし」
「ほんとに特集してよ、凄い木炭ガスなんでがす。
ヘマして爆発するとガス発生釜のフタが成層圏まで飛ぶんでがす。 翼もないのに ・・ 」
「名人、このおとこ 無視しましょう」
「でな、フックから外れたあとは風まかせじゃ。 どこに飛んでゆくのかは運まかせじゃ。
えーじゃろー ロッケンなヒッピーの世界じゃー」
「それですぅー それこそがボクらのロマンだったんじゃないですか。
なのに、なのに無線機つけてペラ付けて、堕落このうえなしだぁ〜 うっうっう」
「泣くな。 オメいつから泣き上戸になった。
堕落だの落ちる用語はご法度だって言ったっぺよ。
どーして無線機とペラの時代になったのかを話すまでは泣かれては困るぞ」
「めいじ〜ん はやく話してくださいましな。 ボクは泣きたい、ひこうき雲でー」
「やい うなぎ屋、ゆーみんスペシャル のカラオケを回せ!」
「だんなあ〜 うちはうなぎ屋でがすが、いたってポリシーなしのごじゃっぺですからスッポンもやっていますぅ〜」
「スッポンが どーしたあーっ」
「へい、かみなり雲 しか用意がありませんー」
おあとがよろしいようで。
3 につづく
写真の説明
前回号にて予告しました Amazon の赤い吹き流しが入荷しました。
中国郵政の火車と貨物機に乗ってチベットネパール国境近くから長い旅をして来ました。
チベット・ネパールは山岳信仰と色とりどりの三角旗のふるさとですから吹き流しも綺麗ですね。
かの地では風が強すぎるので吹き流しより三角旗のほうが屋外では安全なのかも知れません。
長い旅を終えいま異国の風をはらんで竿の先、たたみジワを伸ばす音が聞こえますねえ。 「シワヮーッ」
旗や吹き流しは風になびいてこそですなあ。
日本でも普段からもっと旗を立てましょうよ。
さて、さらに写真に注目すべきは吹き流しを支えるその棹。
この場合竿というより棹が適当かと。
竹棹の曲がり具合の妙が筆舌に尽くし難いほどに美しいと自慢しておりますがいかがでしょうか。
熊のテリトリーの奥山に踏み入ったおしぐれさん、見つけたときは膝が震えたそうです。
熊の足跡が斜面に続いていたからなのか見つけた喜びからなのか不明ですが、ひと目ぼれさが勝って怖さを忘れて採ってきた竹なのですねえ。
そして棹を地面に突き刺す石突きの部分、ここにも注目です。 素材は 「うし殺しの木」
かつて北関東下野の鬼怒川や那珂川には鮎や鮭を獲る専業の川漁師がいました。
幼少期のおしぐれさん、「なりたい職業」ナンバー2が川漁師でした。
堂々のナンバー1はこどもにしては渋く村の鍛冶屋でした。
小学校の帰り道に必ず寄っては師匠の見習いをし、夕方になっても帰らないので心配した婆やが提灯を点けて迎えに行くと、鍛冶屋の爺さんと焼き鮎を肴に晩酌をやっていたなあ〜んてのはしょっちゅうでした。
鍛冶場では鋤(すき)鍬(くわ)や鉈(なた)も打ちましたが鮭漁の銛(もり)を打たせたら名人と言われた爺さんでした。
自分が川で鮭を銛で撃つならば、こーだよなー あーだよなあー と実際にフィールドに出てシミュレートしながら曲げを工夫し重さのバランスを取った銛は正確に鮭の肩を貫き、イクラや白子に傷をつけることはなかったといいます。
漁師たちが操った特殊形状の木造小舟を笹っ葉舟と呼びました。 笹の葉のカタチのひとり乗り川舟を作る舟大工にも名人がいました。
この時代、ひとさまの命にかかわるモノを作るひとの多くは名人と呼ばれていました。
いい加減なモノを作るひとは村に残れなかった厳しい理由から、おしぐれさんの廻りには名人しか居なかったのです。
考えてみたら凄い時代だったと言えましょう。
笹っ葉小舟は前後に細長い船形が急流で舳(読み:じく 意:へさき)の向きを安定させ、常に上流を向くので竹棹一本で流れを遡るのに有効であったといわれています。
漁師が小舟を進める水棹(みざお)は自分で作るのが鉄則です。 水中で岩を蹴って砂利と格闘するその先端部には必ず「うし殺し」を鋳込んでいた。
極めて硬い木である 「うし殺しの木」 を打ち込んで、抜けないように鉄のタガで締めて仕上げるのです。
もちろんそのタガは名人鍛冶屋が出雲の玉鋼(たまはがね)から打ち出しました。
ノコギリを受け付けないほど硬いうし殺しの木は拒鋸(きょきょ)の木とも呼ばれます。 ヤスリで削って鋳込みます。
水中で流れる小石と長時間戦って”ささくれ”ないのはこの木だけです。 さかなクンならぎょぎょですね。
昭和中期のとび職さんが初回東京オリンピックのスタジアム建設の杭を一日中打ち続けて有名になったあの鉄の大ハンマーの柄がこの木でした。
硬いばかりではなく打ち下ろしの反動を上手に生かすしなやかさもあったのです。
剣聖塚原卜伝が宮本武蔵と打ち交わしたという木刀が卜伝の墓所のある霞ヶ浦鹿島の神社に伝わっています。 墓誌に丑殺しのうんぬんと刻まれているそうです。
うし殺しの名の由来はもはや書く必要はありますまい。
下野は優れた牛肉の隠れ産地ですからなあ。
この木は関東の山野に自生し、株のすぐ上から四方に枝幹が派生する茶色の低木落葉樹です。
ですが似た樹種は多くひと目で「うし殺し」と見分けのつくひとは少なくなりました。
おしぐれさんは前回号のあと熊の山に竹を採りに入って見つけたのですが、そのときは嬉しくて熊の出没を忘れて舞い踊ったたそうです。
先年猪山で舞茸を見つけたときもそうでした。
このひとは嬉しいとメガネが落ちるんでねぐ、ロックでヒップなダンサーになるんです。
ひとしきり踊ったあとで、竹切用の鉈(なた 作:下野俊水)を1本ダメにする覚悟で何度も振り下ろし、汗びっしょりになって一幹切り取りました。
そのタダならぬ百鬼の形相に幽霊迫る鬼気の様、裂帛の気合に鉈の煌めき物凄く、雷鳴さえ木霊したといいますな。
背後の藪の陰から一部始終を見ていた熊がいました。 抜かしかけた腰を押さえてそーっと踵を反し、静かに離れて行ったそうでございます。
このひとには笛などいりませんな。
次回はウルシの木を避けながら沢筋を登って行ったおしぐれさんが人食い猪に遭遇したハナシがいいですか?
それとも大岩をどかしたら野槌(つちのこ)が冬眠していたハナシがいいでしょうか?
なにっ! グライダーにプロペラが付いている訳を早よう説明せよってかに?
いやー 忘れておりましたなあ。 それでは 3 でお会いしませう。